※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています
柴犬の噛み癖は放っておくと危険

こんにちは。柴犬と赤ちゃんと生活しているてんちゃんママ(Instagram)です。
柴犬の甘噛みや噛み癖がなかなか治らない…と悩んでいる方も多いですよね。私も実際愛犬の甘噛みを治すのが大変で1歳くらいまで続きました。我が家の愛犬に一番効果があったしつけ方法は「無視してその場を離れること」でした。
子犬のときの甘噛みは可愛くて許してしまいたくなりますが、放っておくと本気噛みする原因になります。そこで、本記事では柴犬の噛み癖のしつけについて以下のことをまとめています。
この記事の内容
- 甘噛み・噛み癖の原因
- 子犬・成犬の噛み癖の違い
- 甘噛み・噛み癖の対処法
- 甘噛み・噛み癖を治すしつけの方法
- 噛み癖のしつけの注意点
- 子犬の甘噛みはいつまで続くか
- 主従関係について
甘噛み・噛み癖の原因
柴犬が甘噛み・本気噛みするのはさまざまな原因が考えられます。以下で甘噛み・噛み癖の原因について紹介するので、愛犬がどれにあてはまっているか考えてみてください。
乳歯の生え始めのかゆみ

子犬期は歯が生え変わるので、違和感やかゆみで甘噛み・噛み癖に発展している可能性があります。生後1ヶ月頃~8ヶ月頃までに乳歯から永久歯に生え変わるため、この時期であれば歯がかゆい可能性が高いでしょう。
具体的には、飼い主さんの手や服、ゲージの柵や家具の端などあらゆるものを噛みたくなります。噛んでいいおもちゃなどを用意し、噛んではいけないものを正しく教える必要があります。
欲求

口を開けて歯を当てて甘噛みしてくる場合は、構ってほしいという欲求を伝えている可能性が高いです。本来犬は、犬同士でじゃれ合ったり親に甘えたりするときは、噛んでスキンシップを取ります。
そのため、人間にも同じように「遊ぼう!」と訴えて噛む行為を行ってしまいます。親犬や兄弟たちと触れ合う中で噛む加減を覚えるものですが、生後間もないうちにお迎えした場合、噛む加減を覚えないまま育ってしまっている場合が多いです。

ほかにも「おやつがほしい」「散歩に行きたい」などの欲求を訴えている場合もあるよ!
甘噛みを治すには、甘噛みしているときに欲求に応えないようにすることが大切です。欲求に応えてしまうと、甘噛みしたら飼い主さんに構ってもらえると学習してしまう可能性もあるので注意しましょう。
抵抗

柴犬が噛む理由には、一定の行為に抵抗している場合もあります。犬は喋れないため、噛むことで嫌なことを人間に伝えているのです。
特に柴犬は、ベタベタと触られたり抱っこされたり過度なスキンシップを嫌う子が多いです。そのため、撫でまわしたりしっぽを触ったり足をさわったり・・・過度なスキンシップに噛んで「やめて!」と伝えている可能性があります。

自分が嫌なことをたくさんされたら、どう思うか考えてみてください。
愛犬とスキンシップを取りたいなら、少しずつ始めることが大切です。触れたら褒めるを繰り返して徐々に時間を伸ばしていき、愛犬にとって楽しい時間になるように工夫していきましょう。
本能の縄張り意識

柴犬は縄張り意識が強い犬種のため、自分の縄張りに入ってきた人に対して噛むことがあります。警戒心が強いため、初めての人には特に恐怖心やストレスを感じています。
急に触ってきたり近づいてきたりした場合、恐怖で咄嗟に噛んでしまう場合があるため注意が必要です。初めて触れ合う人の場合、飼い主さんが仲良く話す様子を見せる、匂いをかがせてから触れ合う等工夫する必要があります。
特に性格が臆病な子が本気噛みをするケースが多いので、人(刺激)に慣れさせたり、主従関係を築いて飼い主がコントロールしてあげることが大切です。
ストレス

犬はストレスが原因で、物や人、自分の皮膚を噛むこともあります。犬はストレスが溜まると異常行動を起こす場合があり、物や人に噛みつく行為もその一種です。
ストレスの原因には、運動不足・スキンシップ不足・環境の変化などが挙げられます。ペットホテルに預けた後、引っ越しをした後など、さまざまな理由が考えられるでしょう。
犬の気持ちを理解するのは難しいことなので、とにかくスキンシップと運動を意識して行ってあげましょう。柴犬の散歩時間は、1日1時間程度するのが望ましいです。散歩できないときは、室内でボール遊びをしたりノーズワークを使ったりして愛犬が退屈に感じないようにしてあげてください。
病気

犬が突然本気噛みするようになった場合は、病気の可能性も考えられます。例えば脳の異常や水頭症・狂犬病などの病気の症状には、「凶暴化」という症状が見られることが実際にあります。
他にも、抱き上げたときに痛いところを触られて、犬が痛みでびっくりして噛むなどのケースもあります。
そのため、普段は噛まなかったのに、急に噛むようになった、他にも気になる症状がある・・・などの場合は、早めにかかりつけの動物病院に受診しましょう。
恐怖・不安な気持ち

暴力・暴力などの間違ったしつけによって、犬が恐怖を感じて噛み癖に発展するケースもあります。マズルコントロールや大声で叱る、暴力などは、恐怖で犬をコントロールするしつけ方で、飼い主さんに恐怖心を持つきっかけとなってしまいます。
大好きな飼い主さんでも、身の危険を感じるほど恐怖を感じてしまえば逆効果です。甘噛みを直すために始めたのに、本気噛みするようになってしまう子も少なくありません。
しつけは、愛犬の性格やペースに、褒めて伸ばす方法が一番効果的です。一度恐怖を感じると慣れさせるのが非常に難しいので、暴力・マズルコントロールなどは絶対にやめてあげてください。
子犬・成犬の噛み癖で違うのは?

噛み癖になる原因は、子犬か成犬かによって少し違いがあります。以下で子犬と成犬の噛み癖の原因について解説するので、愛犬の年齢に合わせてチェックしてみましょう。
子犬の噛み癖の原因

- 歯の生え変わりでかゆい
- 抵抗している
- 興奮している
- 構ってほしい・甘えている
成犬の噛み癖の原因

- 恐怖・ストレス・不安を感じている
- 異常の異常などの病気
- 飼い主を下に見ている(主従関係ができていない)
甘噛み・噛み癖の対処法
甘噛み・噛み癖をする子は、できるだけ早くしつけをしてあげてください。早ければ早いほど学習してくれるのが早いです。甘やかないことが愛犬のためでもあるので、ぜひ根気よく行ってあげてくださいね。
噛み癖を治すしつけをする
噛み癖がくせになってしまう前に、早めに噛み癖を治すしつけをしましょう。構ってほしい・散歩につれていってほしい・怖いなどどんな理由があっても噛んではいけないということを学習させます。しつけを始めるのが早いほど学習してくれるのが早いです。
カミカミできるおもちゃを与える

子犬期の歯の生え変わりによる甘噛みは、カミカミできるおもちゃを与えると改善する場合があります。木のおもちゃやガムなど噛み応えがあるものを与えると噛まなくなったという人も多いです。子犬に与える場合は、おもちゃなどの対象月齢をチェックして安全なものを選んであげましょう。
ストレスを解消させる

ストレスで噛み癖がついている場合は、ストレスを発散させる必要があります。ストレスの原因は、運動不足・コミュニケーション不足・環境の変化などさまざまな原因があります。考えられるストレスの原因を見つけ出し、愛犬のストレスを解消してあげましょう。
社会化トレーニングで刺激に慣れさせる

恐怖心や警戒心で噛み癖がついている場合は、社会化トレーニングで刺激に慣れさせましょう。元々警戒心が強い犬種ですが、性格や社会化期の過ごし方によって臆病になっている子もいます。社会化トレーニングとは、人・車・音などさまざまな刺激に慣れさせることです。社会化期は生後3週間~14週が一番慣れやすい時期だといわれています。
愛犬と信頼関係を築く

愛犬と飼い主さんに信頼関係が築けていれば、噛みつくことはありません。愛犬と信頼関係を築くには、スキンシップを取る・安心させてあげる・適切な指示を出すなどの方法があります。感情的に接したり、指示が毎回違っていたりすると犬も不安になってしまうので注意が必要です。
本気噛みはドッグトレーナーなどのプロに力を借りる

本気噛みを繰り返すようであれば、ドッグトレーナーなどプロの力に頼りましょう。柴犬の噛み癖を治さずに放っておくと凶暴化する恐れがあります。実際に飼い主さんが手に負えなくなり、柴犬を手放してしまう人も多くいます。最初は甘噛みでも体罰などの誤ったしつけ方をするとひどくなる場合もあります。
甘噛み・噛み癖を治すしつけの方法
ここからは、私が実際に愛犬の柴犬の甘噛みを治したときのしつけ方法を紹介します。指示は「ダメ!」「ノー!」「こら!」でもなんでもいいので、何でもやめさせるときは同じ合図を使用してください。
手を噛んできたときのしつけトレーニング

- 甘噛みをしてきたら低いトーンで「ダメ」という
- その場を10~20秒程度離れる
- 甘噛みする度繰り返す
- 「ダメ」といって離すようになったら「いい子!」と褒めてあげる

実際にドッグトレーナーに相談したところ、愛犬から離れる時間が長すぎると要求吠えなど違う問題行動に繋がってしまうそうです。短くても噛んだら飼い主さんがどこかへいってしまうと学習すればいいので、長い時間離れるのはやめましょう。愛犬が理解しやすいように「ダメ」はにらみつけるなど表情をつけるのがポイントです!
ものを噛んだときのしつけトレーニング
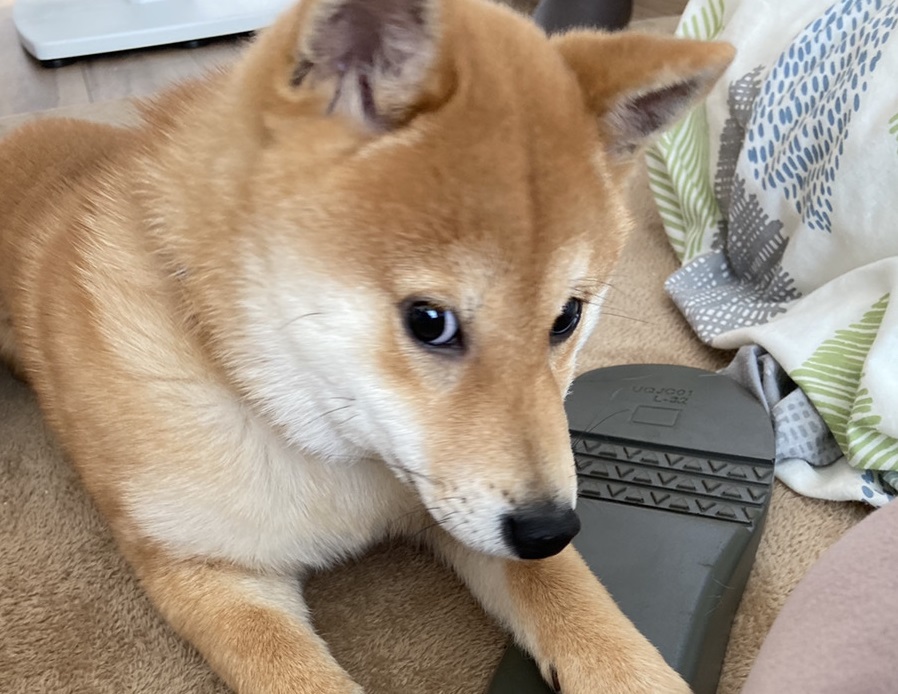
噛み癖のしつけの注意点

噛み癖をしつける際は、以下のようなことに注意してください。誤ったしつけ方をすると、違う問題行動を起こすリスクもあるので注意が必要です。
体罰・大声で圧力をかけるのは絶対ダメ

暴力をふるう・大きな音や声で驚かす・閉じ込めるなど、愛犬に圧力をかけて叱るのは絶対にやめてください。愛犬の信頼関係が崩れ、噛み癖がさらに悪化する場合もあります。
また、ドッグトレーナーや訓練所でも、体罰・天罰方式で教えるところも未だにあるそうです。噛み癖を治すつもりがさらに凶暴化する事例もあるので、プロに頼むときもどんなしつけ方法なのか必ず確認してください。
興奮していたら落ち着いてからトレーニングする

犬が興奮しているときは、利く耳をもってくれないことが多い傾向にあります。一度その場を離れて、愛犬が少し落ち着くのを待ちましょう。遊んでいるときにじゃれて噛んでくる場合は、その場を離れるだけで噛み癖が落ち着くことが多いですよ。
しつけ方法が合っていないと感じたらすぐにやめる

この記事では紹介しませんでしたが、噛み癖を治すには無視する・大きなリアクションを取る・低い声で怒る・指を喉の方へ突っ込むなどさまざまなしつけの方法があります。愛犬の性格によって効果的なものが違うので、場合によっては少し辛いトレーニングが必要になるケースもあるそうです。
しかし、嫌な経験がトラウマになってしまうこともあるので、しつけ方法がその子に合わないと感じたらすぐにやめてあげてください。色々試しても噛み癖が治らない場合は、無理をせずプロに相談するのをおすすめします。
子犬の甘噛みはいつまで続く?

子犬の甘噛みは、生後3~8ヶ月程度で落ち着く傾向にあります。ただし、甘噛みをやめさせるしつけをしておく必要があります。子犬のうちに噛み癖を治すしつけをしておかないと、成犬になっても噛み癖がついてしまうので事故防止のためにも必ず子犬のうちからしつけておきましょう。
主従関係を作っておくのも重要!

犬は群れで生きる生き物なので、主従関係を作っておくのが重要です。主従関係とは、飼い主さんのことをリーダーと認め、信頼関係が築けている関係です。飼い主のいうことをきいてくれるので、愛犬を危険から守ることもできます。愛犬を甘やかしたくなる気持ちもありますが、愛犬のためにも人間主導でいることを心がけてください。

我が家の愛犬も最初は構い過ぎて主従関係ができていませんでした。
「このままではまずい!」と感じたので、玄関・ドアから出るときはまず私、ご飯も先に食べてから愛犬に出す・散歩は引っ張ったら動かないなどさまざまな訓練を行いました。正直本当に大変なので、社会化期にトレーニングしておくのをおすすめします。
柴犬の噛み癖としっかり向き合ってほしい
柴犬の噛み癖は治らないと諦めるのではなく、しっかりと向き合ってあげてほしいです。このくらいの甘噛みならいいや…と思っていても、いつの日か本気噛みをしてしまうこともあります。さまざまなしつけ方法を試しましたが、根気よく無視してその場を離れるしつけを繰り返すのが一番有効だったので紹介しました。






コメント